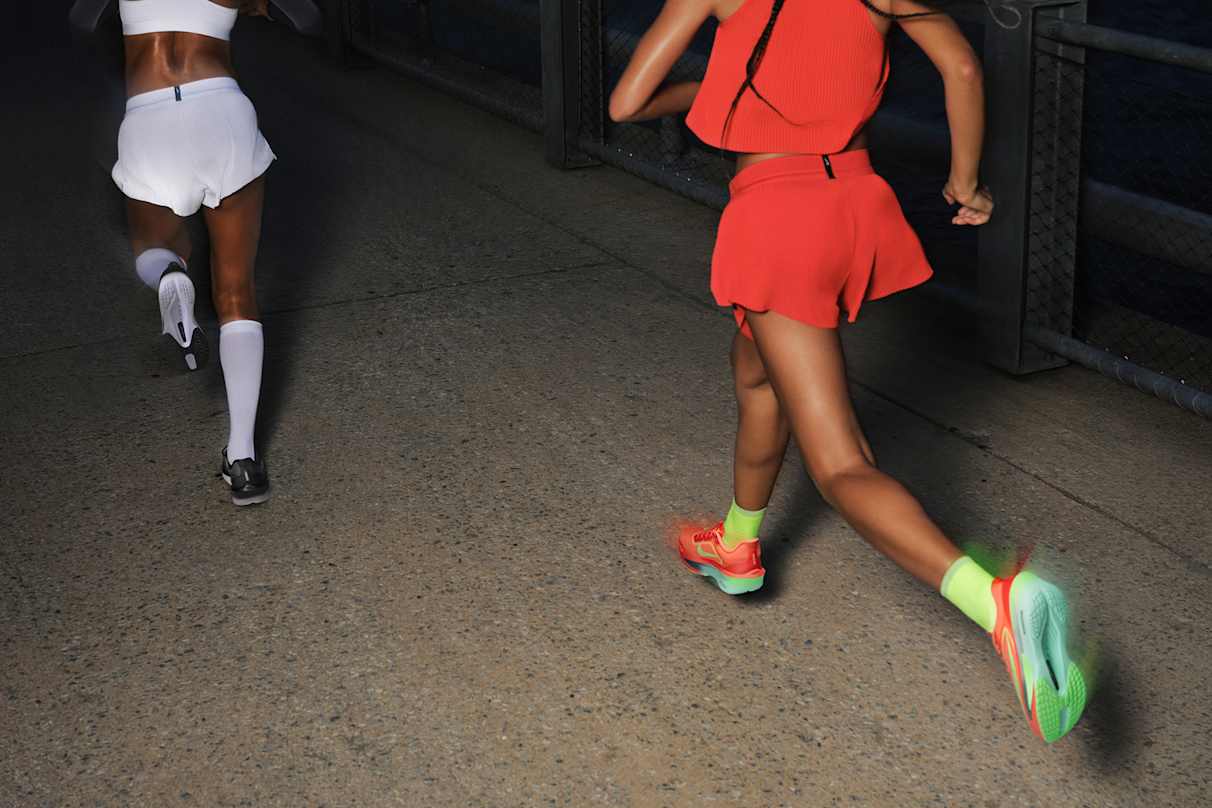ランニングで活性化する7つの筋肉群
アクティビティ
ランニングによって活性化するいくつかの主要な筋肉群。 ここでは、その部位やストライドごとに発揮する役割を紹介する。

ランニング中は、体の複数の筋肉が懸命に働き、各部位でパワーを発揮する。 ペースを上げたり、坂道を上ったりするときに燃焼する筋肉もあれば、 ランニング後にいつもと違う痛みを引き起こす筋肉もある。この場合、けがをするのではないかと心配になるだろう。
走る際にどの筋肉が使われるかを理解することで、それぞれの筋肉が役割を十分に果たせるようになる。 また、痛みやけがを引き起こす前に、潜在的な弱点を特定するのにも役立つ。
「筋肉それぞれの機能を知ることは有益ですが、同じくらい重要なのは、すべての筋肉が単独で機能しているわけではないということを知ることです」と語るのは、ルーク・ベネット博士(認定ストレングス・コンディショニングスペシャリスト(CSCS)の有資格者であり、 カイロプラクティック専門医。ノースカロライナ州のTOPTEAM Sports Performanceでランナーを担当している)。
すべてが適切に機能していれば、筋肉が連動し、スムーズで安定した走りになる。 しかし、連鎖の中に弱い部分が1つあると、ランニングメカニクスが乱れ、効率の低下やけがにつながる可能性もある。
ここでは、ランニングで使われる筋肉について説明しよう。
ランニングの歩行サイクル
ランニング時の筋肉の働きに対する理解を深めるには、ランニング時の歩行サイクル(一歩ごとの脚の動き)を意識することが有効だ。
2021年に『International Journal of Physical Education, Fitness and Sports』で発表された研究によると、ランニングの歩行サイクルには主に2つのフェーズがある。
- スタンス、つまり片足が地面に着いている時間
- スイング、つまり両足が空中にある時間
歩行サイクルは、片足が着地するスタンスフェーズから始まる。 足を地面から持ち上げて前に移動させると、スイングフェーズに入る。 スイングフェーズの最初は、つま先が下を向き、膝は少し曲がっている。 そこからのスイングフェーズで膝をさらに曲げ、つま先を上に向けることで、次のサイクルに備える。 走り終えるまで、このパターンが続いていく。
ランニングを担っているのはどの筋肉か?
ランニングの歩行サイクルについて説明してきたが、次は、ストライドを伸ばす筋肉について詳しく見ていこう。
1.股関節屈筋
股関節屈筋は、太もも上部の前面にある筋肉群であり、股関節を曲げる働きをする。 ランニング時の歩行サイクルのスイングフェーズでは収縮して脚を前方に引っ張り、スタンスフェーズでは伸びて脚を押し出す。
股関節屈筋はどのようなランでもよく使う筋肉だが、スプリントや坂道でのワークアウトでは使いすぎになる、とベネット博士は言う。 どちらのワークアウトも、膝をさらに強く動かす必要があるため、股関節屈筋の収縮が強くなるのだ。
股関節屈筋は繰り返し縮むため、ランナーは走らない人に比べて股関節屈筋が硬くなりやすいと、スカイラー・アーシャンボー(理学療法士、 理学療法の専門職博士、 認定ストレングス・コンディショニングスペシャリスト(C.S.C.S)の資格を持ち、マサチューセッツ州ボストンのArch Physical Therapy and Fitnessで理学療法士兼パーソナルトレーナーを務めている)は言う。
また、オフィスや自宅で一日座りっぱなしで過ごしていても、股関節屈筋が縮んでしまい、凝りを悪化させる可能性がある。 股関節屈筋が硬いと、ランニング中に股関節を伸ばす距離が制限され、大臀筋の助けも得にくくなる。
2.臀筋
お尻には3つの臀筋がある。 3つの中で最も大きく、最も強力なのが大臀筋だ。 お尻の肉付きの良い部分に位置する大臀筋は、足を地面から蹴り上げてスイングフェーズに移行する際に、股関節を伸ばす役割を担う。
上り坂では、大臀筋をさらに働かせる必要がある。 「坂を上るには、臀筋を使って股関節をより伸ばさなければなりません」とベネット博士は説明する。
また、トップスピードに到達するには、速いペースで股関節を伸ばすため、大臀筋が鍵となる。 2021年に『Medicine and Science in Sports and Exercise』に掲載された研究論文によると、エリートスプリンターは、トレーニングを積んでいないランナーに比べて、この筋肉が有意に大きい。
2番目に大きい臀部の筋肉が、中臀筋。 臀部の外側にある扇状の筋肉が、最も小さい臀筋である小臀筋と連動し、スタンスフェーズで臀部と骨盤を安定させる。
「反対側の脚が地面から離れているときは、中臀筋を使って骨盤を水平に保ち、片側に倒れないようにする必要があります。片足を地面から離すと、重力によってバランスを崩すからです」とベネット博士は述べている。
3.大腿四頭筋
大腿四頭筋とは、太もも前側にある4つの筋肉群。膝を持ち上げるときに股関節を曲げる動きを助ける。 そして、着地するときに膝を伸ばす。
短距離走や上り坂のランでは、膝を強く動かす必要があるため、大腿四頭筋がより強い抵抗を受けることになる。 一方、下り坂では、スピードをコントロールしようと強い伸張性収縮(筋肉は伸びた状態)を行うため、大腿四頭筋にさらに高い負荷がかかる。
「転ばないようにブレーキをかけて動きをコントロールするのは大変な作業です」とベネット博士。
常時ブレーキを効かせるには、筋繊維、関節、腱、靭帯に上り坂を走るときよりも多くの力をかけなければならない、と彼は付け加える。 これが、急な下り坂のルートを走った後に大腿四頭筋がことさら痛くなる理由だ。
4.ハムストリング
太ももの裏側にあるハムストリングは、脚を前に振り出して次の一歩を踏み出す際に膝を曲げる働きをする。 しかし、その主な役割は足で地面を蹴るときに力を生み出すことであり、これがスプリント時の加速の鍵となる。 『Frontiers in Physiology』に掲載された2015年の研究では、ハムストリングが最も活発に働く男性は、スプリント時に最も力を発揮することが示された。
一部のランナー、特に女性は「大腿四頭筋が優位」になりがちだ。つまり、ハムストリングよりも大腿四頭筋により多くの負荷がかかるということになる。
「腰、足首、足の可動性が損なわれて、大腿四頭筋が優位になっている場合もありますが、それは大腿四頭筋とハムストリングの筋力のバランスが悪いせいかもしれません」とアーシャンボーは言う。 ハムストリングの筋力が足りず、ランニングのストライドを均等な力で支えられない場合、その力不足を補うために大腿四頭筋に負荷がかかるのだ。 「いずれ、ランニングで膝が痛くなるかもしれません」とベネット博士は言う。
5.ふくらはぎ
下腿部のふくらはぎの筋肉も、ランニングの歩行サイクルにおいて重要な役割を担っている。 足が接地すると、ふくらはぎの筋肉とアキレス腱(ふくらはぎの筋肉とかかとの骨をつなぐ厚い帯状の組織)がエネルギーを吸収し、蓄える。 次に、地面を蹴り出すときに、蓄えられたエネルギーがふくらはぎの筋肉とアキレス腱から解放され、体を前方へ押し出す、とアーシャンボーは説明する。
実際、腓腹筋とヒラメ筋というふくらはぎの2つの筋肉は、驚くべき力を発揮する。 『Journal of Experimental Biology』に掲載された2012年の研究によると、腓腹筋(ふくらはぎにある太い筋肉)は最大で時速15.5マイル(約25km)の力を生み出す。 このペースでは、腓腹筋が体重の3.23倍に相当する力を生み出すことになる。 一方、ヒラメ筋(腓腹筋の下に位置する筋肉)が発揮する力は、体重の約8.71倍だ。
蹴り出す際に、衝撃を吸収して解放するだけの力がふくらはぎの筋肉にない場合、それを補うために体が力を制限し、けがのリスクが高まると、アーシャンボーは指摘する。
6.腹筋
腹部にあるこの筋肉は、上半身と下半身をつなぐ役割を持つ。 ランニング中に骨盤と背骨を安定させ、「ぐらつくことなく、脚をより効率的に動かせるようにしてくれます」とベネット博士。 「この筋肉が全力で働いて回転をコントロールしてくれるので、体が前後にねじれてエネルギーを浪費することがありません」
片脚に体重を移すスタンスフェーズでも、腹筋を使う。 「片脚を上げるたびに倒れないよう安定させるために、軸脚側で腹筋を働かせなければなりません」とベネット博士は言う。
スプリントの際は、胴体が回転しないよう腹筋がとりわけ力を発揮する。 アーシャンボーは「短距離走では脚の動きがかなり速いため、安定させるために腹筋により働いてもらう必要があります」と話す。
7.上半身の筋肉
ランニングは主に下肢を使う運動だが、上半身も使っているのだ。 ランニング(またはウォーキング)では、自然に腕が動く。
「後方に移動する脚と反対側の腕を前方に振ることは、バランスをとる上で重要な要素です。この脚の非対称性によって回転したり転倒したりせずに済むのです」とベネット博士は言う。
腕を振ることは、バランスを保つのに役立つだけでなく、推進力を与え、勢いをつける効果もある。 アーシャンボーによれば、広背筋(背中にある大きな扇形の筋肉)と肩が腕の動きを支える。
背中と肩は、ランニング中に直立姿勢を保つ上でも重要な役割を果たす。これはランニングエコノミーの向上につながる。つまり、効率的に酸素を使用してペースを維持できるようになるということだ。
「直立姿勢を維持することで、整った姿勢が維持され、体内でエネルギーを最も効率的に運べるようになります」とアーシャンボーは言う。
文:ローレン・ベドスキー